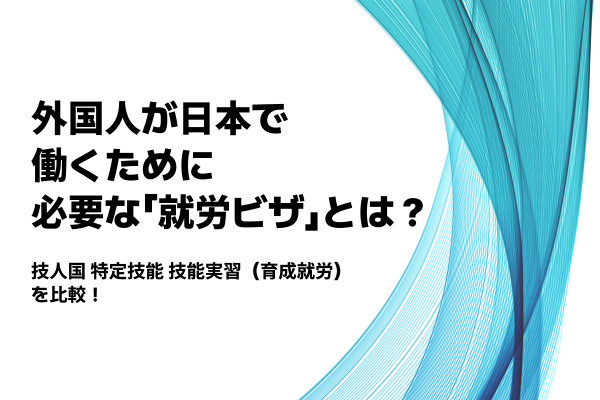【代表コラム】第2回目 岐路に立つ日本:世界の歴史から学ぶ共生社会への道のり
PERSOL Global Workforce代表取締役社長 多田盛弘

はじめに:日本と移民
新型コロナウイルス感染症による出入国制限が緩和されて以降、国内の外国籍人口が急激に伸びている。昨年1年間だけで在留外国人数は35万人以上も増加し、その総数は376万人に達した。日本政府は一貫して在留外国人に対して「移民」という言葉を用いないが、現在の在留制度では多くの外国人に長期就労と家族呼び寄せの可能性が開かれており、実質的には移民の受け入れが加速していると言えよう。
日本は島国という地理的特性も相まって、世界的に見ても、最も多様性の低い国の一つである。例えば、多様性を示す指標の一つである「Ethnic Fractionalization Dataset」 によれば、日本は調査対象157カ国中で民族多様性が最も低いとされている。そのような日本で在留外国人が急増することは、社会的な摩擦や課題が顕在化しやすい状況を生むことを意味する。最近では、報道などを通じて外国人の増加に伴う課題や懸念が伝えられる機会も増えた。日本は今後、欧米のように移民国家へと向かうのか。そうであるならば、我々は移民先進国の経験から何を学ぶべきなのだろうか。本稿では、現状の課題を世界の事例と比較しつつ、これからの日本の姿、そして私たち自身の暮らしのあり方を考察していく。
第1章:統合なき移民
日本の移民政策を理解する上で、まず知っておくべきは、過去から現在に至るまで外国人受け入れの根底に流れる思想である。それは、外国人を「一時的に労働力を補う助っ人(ゲストワーカー)」と見なす、という考え方だ。この思想が、まるで「見えない壁」のように、外国人に関わる諸制度や社会の仕組みの隅々にまで張り巡らされている。2019年に新たな在留資格「特定技能」が創設されるまで、第一次産業や製造業、サービス業などで働く外国人の多くは、正規の「労働者」としてではなく、国際貢献を名目とした「技能実習生」や、学業の傍ら働く「留学生」という立場であった。彼らは短期滞在を前提とした人材と見なされたため、300万人を超える規模に達した在留外国人が社会に与える影響は過小評価され、彼らを社会の一員として受け入れる「社会統合」の視点は長らく等閑視されてきたのである。
このような日本の移民政策は「統合なき移民(Immigration without Integration)」と評される。つまり、人手不足を補うために外国人を「労働力」として受け入れながらも、彼らを社会の一員として包摂するための国家的な戦略が欠如している状態を指す。
こうした日本の政策は、国際的な物差しで見るとどう評価されるのか。「移民統合政策指数(MIPEX)」 という、世界各国の移民政策を比較評価する、いわば「通信簿」が存在する。2020年の調査で、日本の総合スコアは100点満点中47点。これは調査対象となった先進国の平均(49点)をも下回る結果である。「移民」という言葉を避け、「短期のゲスト」と見なしてきた在留外国人が、今や総人口の3%に迫る勢いである。もはや社会統合という課題から目を背けることは許されず、彼らが日本社会の一員として円滑に「統合」されるための仕組み作りが急務となっている。
第2章:移民先進国の事例
日本が「統合なき移民」で試行錯誤を続ける一方、世界の国々は、日本よりずっと前から移民と共に社会を築く経験を積み重ねてきた。その歩みは決して平坦ではなく、多くの成功と、そして痛みを伴う失敗に彩られている。彼らの物語から、私たちは何を学べるのだろうか。
ケース1:アメリカ
「人種のるつぼ」「移民の国」。これらの言葉が示す通り、アメリカはまさに移民と共に形成されてきた国家である。多様性を国是とし、移民受け入れは主に以下の3つのルートで構成されている。
1. 家族呼び寄せ: アメリカ市民や永住権保持者が、親や配偶者、子どもといった近親者を呼び寄せることができる。
2. 雇用ベース: 高度な専門性を持つ人材から不可欠な労働者まで、経済活動に必要な労働力を受け入れる。
3. 多様性ビザ: 通称「グリーンカード抽選」で知られ、歴史的にアメリカへの移民が少なかった国々の人々にも門戸を開き、社会の多様性を維持・促進する。
アメリカモデルの最大の特徴は、「努力すれば、あなたもアメリカ市民の一員になれる」という明確なメッセージが国家レベルで示されている点にある。このメッセージが、移民たちのアメリカ社会への定着を促す強力なインセンティブとなっている。国がトップダウンで統合策を施すのではなく、家族やエスニック・コミュニティの相互扶助を通じて、移民が自律的に社会へ溶け込んでいくのがアメリカ流のスタイルと言えるだろう。
その一方で、アメリカは何百万人もの「非正規滞在者」を抱えるという「影のシステム」も存在する。この問題は絶えず政治的な火種となり、現代アメリカ社会の分断を象徴する一因となっている。
ケース2:ドイツ
第二次世界大戦後のドイツは、日本と同様に深刻な労働力不足に直面し、トルコなどから多くの「ガストアルバイター(ゲストワーカー)」を受け入れた。当時のドイツ政府は、彼らをいずれ母国に帰る「一時滞在者」だと考えていた。これは、移民という実態から目を背け、外国人をあくまで一時的な労働力と見なすという点で、かつての、そして現在の日本の状況と酷似している。
ドイツ政府が社会統合政策を軽視した結果、ドイツ語を話せない移民コミュニティが形成・孤立し、「パラレル・ソサエティ(並行社会)」と呼ばれる深刻な社会問題が生まれた。この苦い経験を教訓に、ドイツは2005年1月、新たな移民法を施行し、移民のドイツ社会への「統合(Integration)」を国家の重要課題と位置づけた。その対策の柱となったのが、国が主導する義務的な「統合コース」の導入である。これは、移民にドイツ語と、ドイツの法秩序や文化、価値観を学んでもらうための、いわば国営のウェルカム・プログラムである。
ケース3:スウェーデン
かつてのスウェーデンは、世界で最も先進的で人道的な移民政策を持つ国として知られていた。MIPEXのスコアも世界トップクラスを維持し、労働、教育、差別禁止など、ほぼ全ての分野で最高水準の制度を誇り、まさに移民統合の「優等生」と見なされていた。しかし、このスウェーデンの経験こそ、日本にとって示唆に富む重要な教訓を内包している。それは、いかに手厚く、完璧に見える制度を構築したとしても、社会統合は容易には達成できないという厳しい現実である。
2015年以降、シリアなどからの難民が急増したことで、スウェーデンの住宅供給や教育現場が逼迫し、一部の地域での犯罪率の上昇などが、移民問題と直結させて語られるようになった。その結果、反移民を掲げるスウェーデン民主党が支持を拡大し、政府は庇護申請や家族呼び寄せの要件を厳格化するなど、大幅な政策転換を余儀なくされている。
優れた制度設計もさることながら、移民の受け入れを社会が吸収できる範囲(社会的受容能力)に合わせて慎重に管理し、国民全体の幅広い合意形成を不断に続ける努力がいかに重要か。スウェーデンの教訓は、理想だけでは乗り越えられない壁の存在を、私たちに突きつけているのである。
第3章:ケースから見る日本の課題と解決策
これら欧米の教訓から、私たち日本は何を学ぶことができるのだろうか。
まず、日本はアメリカのような多様性を前提として建国された国とは対極にあり、前述の通り、世界で最も民族的多様性の低い国の一つである。したがって、アメリカのように社会全体が移民を自律的に統合していくというモデルをそのまま模倣することは困難であろう。しかしその一方で、多様性を誇るアメリカでさえ、非正規滞在者への反発が政治的な分断の大きな火種となっている事実は、受け入れのルールを厳格に管理することの重要性を示唆している。この点は、不法入国や不法滞在が社会問題化しつつある日本にとっても他人事ではない。近年の国政選挙において、外国人材の受け入れのあり方が主要な争点の一つとして浮上しているのも、こうした背景があるからだ。日本政府としても「共生社会の実現」と「不法滞在者の厳格な管理」という二つの方針を明確にしており、アメリカの事例は、適正な受け入れの仕組みやルートを管理することの重要性を裏付けている。
次にドイツの事例だが、これは日本が最も教訓とすべきケースと言えるだろう。「ゲストワーカー」という発想から出発した点が日本の現状と酷似しており、もし社会統合の努力を怠れば、日本もまたドイツが経験したような「パラレル・ソサエティ」の形成という深刻な事態に直面する可能性は極めて高い。「特定技能」という長期就労と家族帯同の道を開く在留資格が導入された今、日本における外国人労働者はもはや短期的なゲストではなく、家族と共に地域社会を構成する「隣人」であり「パートナー」へと変容しつつある。だからこそ、ドイツと同じ過ちを避けるため、日本社会として外国人を受け入れるための統合の仕組みを早期に確立する必要があるのだ。
最後に、スウェーデンのケースから日本が学ぶべきは、社会の「受容能力(キャパシティ)」の重要性である。社会統合を意識し、高度な仕組みを構築したスウェーデンでさえ社会的な混乱が生じたという事実は、制度を整備すれば万事解決するわけではないという厳しい教訓を与えてくれる。日本の外国人受け入れ人数は、主に産業界の労働力需要と強く連動している。技能実習や特定技能といった制度は、産業ごとの人材ニーズに基づいて受け入れ人数が設定され、国内の人口減少を背景にその数は増加傾向にある。しかし、その議論には、日本社会全体や、実際に彼らを受け入れる地域コミュニティのキャパシティという視点が欠落している。労働者は同時に地域コミュニティの一員でもある。単に産業界の労働力需要のみを基準とするのではなく、地域社会が彼らを受け入れ、支えることのできる「社会的受容能力」を真剣に議論し、その上限を見極める必要性を、スウェーデンの経験は教えてくれる。

第4章:まとめ
ここまで、日本の移民政策が抱える問題と、世界の国々との比較から得られる教訓を考察してきた。現状と課題をまとめると、以下のようになる。
1. 日本の少子高齢化と産業維持のため、外国人材の受け入れは今後も拡大する。
2. 在留資格制度の変更に伴い、外国人労働者は短期滞在者から長期的な「移民」へとその性格を変えつつある。
3. (アメリカの教訓) 適正な受け入れルートを管理し、不法滞在を防ぐ制度設計が不可欠である。
4. (ドイツの教訓) 社会の分断を避けるため、国が主導する社会統合政策の早期確立が急務である。
5. (スウェーデンの教訓) 制度設計だけでなく、社会全体の「受容能力」を考慮した受け入れ規模の管理が重要である。
このように、在留外国人の増加は日本社会に構造的な変化をもたらし、私たちの生活にも直接的な影響を及ぼす。だからこそ、移民先進国の経験に真摯に学ぶ姿勢が不可欠なのである。
こうした議論は、まだ身近に外国人が少ない地域に住む人々にとっては、どこか遠い国の話のように聞こえるかもしれない。しかし、むしろそうした地域こそ、これから本格的に日本人と外国人の「共生」という課題に直面することになるだろう。
筆者の居住する地域は、日本でも特に外国籍住民の比率が高い。隣接する埼玉県川口市では、外国人人口が約4万人に達し、その比率は7%と全国平均の3%を大きく上回る。このレベルになると、地域の公立学校では一つのクラスに複数の外国にルーツを持つ生徒がいるのが日常となり、生活の中で外国人と接しない日はないと言っても過言ではない。この光景はもはや一部の都市だけの特殊なものではない。現在のペースで在留外国人が増え続ければ、そう遠くない未来に、日本の多くの地域が同様の「多文化共生社会」へと移行していくことは想像に難くない。
これまで国家レベルでの仕組みの必要性を論じてきたが、最終的に外国人と日々接し、コミュニティを形成するのは、その地域に住む住民である。国や自治体の制度設計と同時に、私たち自身の地域コミュニティが主体的に共生社会のあり方を考え、実践していくことが求められる。
外国人が社会に増えることについては、期待と同時に不安の声もあり、様々な意見が存在する。しかし、一つだけ確かなことは、増え続ける在留外国人がもたらす社会的な変化から目を背けていては、欧米諸国が経験したような混乱や分断の轍を踏むことになりかねない、という事実である。これまで世界で最も均質的と言われてきた日本が、否応なく多文化・多民族社会へと変化していく。この現実を直視し、国家レベルの大きな設計図と、私たちの足元である地域社会での具体的な実践の両輪で、いかにして真の共生を実現していくか。今、私たちはその岐路に立たされている。
事例・お役立ち情報をもっと見る
- トップ
- 事例・お役立ち情報
- 【代表コラム】第2回目 岐路に立つ日本:世界の歴史から学ぶ共生社会への道のり
 PERSOL Global Workforce株式会社
PERSOL Global Workforce株式会社